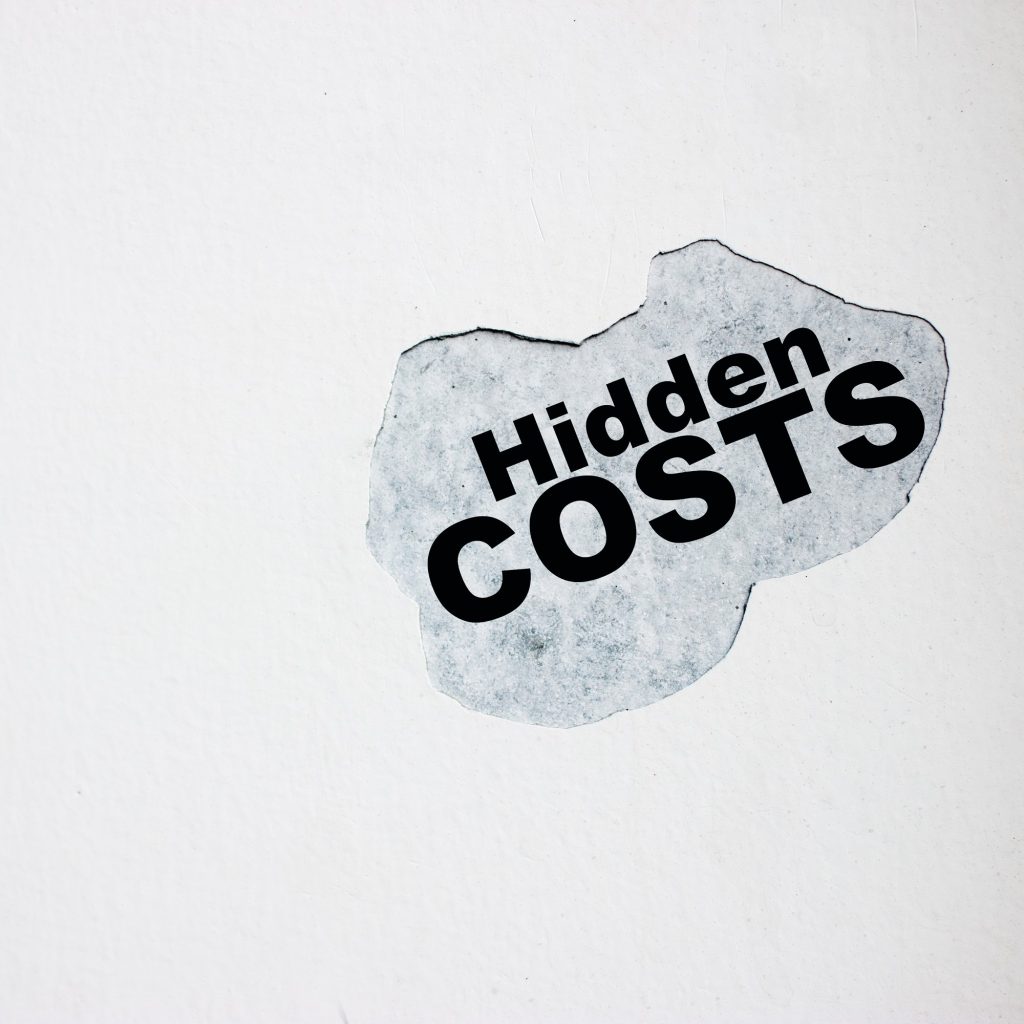- #ACM20(4)
- #APMON(15)
- #ISO4406(8)
- #ISO11171(1)
- #ISO11943(2)
- #ISO14644(9)
- #ISO14698(1)
- #ISO16232(3)
- #ISO21018(1)
- #ISO等級(7)
- #JISB8673(1)
- #JISB9933(3)
- #LCM20(6)
- #LCM30(7)
- #MicroQuick(3)
- #MS200(1)
- #NAS1638(4)
- #NAS等級(4)
- #OilWear(4)
- #PartSens(17)
- #PC5000(5)
- #PC5000/3400(1)
- #PDR(1)
- #PDS.TM(8)
- #SCP(1)
- #SEIKA(4)
- #VDA19(3)
- #VDA19.1(3)
- #イオナイザー(1)
- #インラインサンプリング(2)
- #エアパーティクルカウンタ(1)
- #エアフィルタ(1)
- #オイル(11)
- #オイルの洗浄度(4)
- #オイル測定(6)
- #オイル管理(1)
- #ギアボックス(1)
- #クリーンルーム(12)
- #クリーンルームクラス(1)
- #クリーン製造環境(5)
- #コスト低減(1)
- #コスト削減(1)
- #コンサル(1)
- #コンサルティング(1)
- #サンプリング(2)
- #データセンター(1)
- #トライボロジー(1)
- #ドライルーム(1)
- #バイオ医薬品(1)
- #バッテリー製造工程(1)
- #パーティクルカウンタ(11)
- #パーティクル管理(1)
- #フィルタ(1)
- #フルイド(5)
- #フルイド測定(3)
- #プラントメンテナンス(1)
- #プロセス清浄度(1)
- #ボトルサンプリング(2)
- #メンテナンス(2)
- #リスクアセスメント(1)
- #リスクマネジメント(1)
- #ワニス・スラッジ(1)
- #事例(1)
- #人とくるまのテクノロジー展(1)
- #人の健康(1)
- #企業の信頼性(1)
- #傾斜角センサ(4)
- #光学部品(1)
- #分析(2)
- #加速度センサ(1)
- #半導体製造工程(1)
- #受託分析(4)
- #堆積モニタ(2)
- #宇宙航空(1)
- #展示会(6)
- #工場排水(2)
- #微生物汚染(1)
- #摩耗(1)
- #摩耗管理(1)
- #校正(1)
- #水処理(1)
- #水分混入(1)
- #汚染(1)
- #汚染制御(2)
- #汚染対策(1)
- #汚染管理(2)
- #洗浄工程(3)
- #流動電流計(1)
- #浮遊微粒子(2)
- #液体汚染(1)
- #液封入容量式(2)
- #清浄度検査(3)
- #測定方法(5)
- #潤滑(1)
- #潤滑油(2)
- #潤滑油管理(1)
- #潤滑管理(1)
- #燃料(3)
- #環境問題(1)
- #環境改善(1)
- #環境汚染(1)
- #異物(4)
- #異物分析(1)
- #異物改善(4)
- #異物残渣(1)
- #異物測定(3)
- #異物監視(4)
- #異物監視機材(1)
- #空気清浄度(1)
- #空気清浄度クラス(1)
- #粒子堆積率(1)
- #粗大粒子(2)
- #純水(4)
- #給油(1)
- #膜スプリングマス容量式(1)
- #自動車(4)
- #自動車部品(2)
- #航空燃料(1)
- #落下塵(3)
- #落下粒子(3)
- #表面清浄度(3)
- #製品品質管理(1)
- #規格動向(1)
- #設備保全(1)
- #設備延命(1)
- #診断(4)
- #軽油(1)
- #部品清浄度(4)
- #電子部品(1)
- #飲料水(1)
- #駆動系ユニット(1)
技術情報
2025.10.17
ラジエーターの流体回路は、なぜ清浄でなければならないのか
自動車の冷却システムは、単に温度を下げるための補助機能ではありません。熱マネジメントが揺らぐと、燃費や出力、さらには耐久性や排出ガスまで広範囲に影響を及ぼします。
特にラジエーター、ヒーターコア、インバータ用クーラ、EGRクーラなどの流体回路は、細く長い流路やマイクロチャネルを多数内蔵しており、わずかな汚染物質によっても流量の偏りや圧力損失の増大、熱交換効率の低下といった問題を招きます。
そのため自動車業界では、コンポーネントの清浄度が品質特性として扱われ、欧州を中心にVDA 19やISO 16232に基づく評価/管理が求められているのです。
目次
- 粒子はどこから来て、何を壊すのか
- 粒子以外の脅威:化学汚染、混合不具合、腐食/電食
- 関連機器における教訓:EGRクーラの事例
- VDA 19.1の要求
- 現場での実装ポイント
- 清浄でないことによるコスト
- これからの視点:新技術と清浄度
粒子はどこから来て、何を壊すのか
流体回路に混入する粒子の由来は多岐にわたります。加工バリや切粉、研磨材、シール剤の剥離、ゴムや樹脂の摩耗粉、腐食生成物、搬送/保管中の環境由来の埃などです。
VDA 19.1は、こうした粒子を抽出/捕集/計測/同定する標準手順を定め、顕微鏡観察やSEM-EDX分析による粒径/個数/材質の評価を推奨しています。
冷却回路で問題になりやすいのは、微小断面のチャネルです。ごく少量の粒子でも部分閉塞/流量偏在/局所過熱の連鎖を引き起こし、実効の熱伝達面積を下げます。
圧力損失の増大はポンプ負荷やキャビテーションにもつながります。そのようなリスクに対し、冷却回路に粒子捕集フィルタを組み込む設計は、狭小チャネルの閉塞やポンプ摩耗、過熱を抑制する手立てとして有効であるとされています。
粒子以外の脅威:化学汚染、混合不具合、腐食/電食
清浄度を脅かすのは固体粒子だけではありません。冷却液は多くの添加剤で防食/防錆/消泡などの機能を発揮しますが、使用に伴い添加剤は消耗/劣化します。
その結果、腐食やスケール形成が進み、腐食生成物という二次粒子が増加して、閉塞や圧損の悪化を再燃させます。こうした劣化に対しては、定期的なフラッシングや交換が推奨されています。
さらに、異なる規格/系統の冷却液を混合すると、添加剤同士の反応でゲル化や沈殿が生じ、ラジエーターやヒーターコアの流れを阻害し、過熱の原因になり得ます。 混合は腐食保護の低下も招くため、切り替え時には系統内のフラッシングで旧液を確実に除去することが重要です。
関連機器における教訓:EGRクーラの事例
冷却回路の清浄度が機能に直結する現象は、EGRクーラで顕著です。
EGRクーラは排気ガスと冷却液の熱交換器で、チューブ内面に形成される多孔質の堆積層(ススや粒子)により、熱交換効率が低下します。
VDA 19.1の要求
VDA 19.1は、粒子の抽出/試験方法や清浄度仕様の設定方法を規格化しています。これにより、設計/製造/組立/検査/梱包/物流などにわたる清浄度管理の出来映えを、サプライチェーン横断的に同じ物差しで測れるようになります。
評価手順は大枠として、適切な抽出(液体フラッシング、ブロー、吸引ブラッシング、スタンプ法等)/濾過捕集/重量測定/顕微鏡観察/材質分析(必要に応じてSEM-EDX)/限度値との比較/是正のフィードバックとなります。
標準化された測定と結果のトレーサビリティが、工程間/企業間の改善議論を容易にします。
現場での実装ポイント
機能基準に紐づく清浄度仕様化:
最初に、冷却性能や耐久に直結するボトルネック流路(マイクロチャネル、オリフィス、バルブ近傍、ポンプ摺動部など)を特定します。そのうえで、性能影響を与える粒径/個数の閾値から、VDA 19.1/ISO 16232の粒度区分に沿った限度値を導出します。
標準化された抽出/分析の定常運用:
サンプリング計画を作成し、ブランク管理を行いながら、抽出/濾過/計測/材質分析を定常的に回します。SEM-EDXの自動化ツールの活用により、短時間で多検体を安定評価する運用も可能です。
発生源の根本対策と初期フラッシングの標準化:
加工/洗浄/組立/梱包/保管/搬送の各工程で、バリ/摩耗粉/シール剤剥離/腐食といった発生源を抑えます。車両やサブシステムへの初期充填前には、系内のフラッシングを標準化し、異種冷却液の残留/混合を回避します。
回路内フィルトレーションの設計反映:
狭小チャネルの閉塞/圧損/ポンプ摩耗/過熱に対する保険として、冷却回路内に粒子捕集フィルタを組み込むことを検討します。設計段階での圧損と捕集効率の最適化が鍵になります。
予防保全:冷却液管理
交換周期だけでなく、劣化兆候(変色、濁り、導電率やpHの逸脱)や粒子濃度を基準に点検/交換を実施します。
清浄でないことによるコスト
清浄度を疎かにすると、見えないかたちでコストが積み上がります。
第一に、通路の閉塞や堆積は熱伝達を損ない、同じポンプ動力で得られる冷却量が低下します。それを補うためにファンを強めれば電力/燃料消費が増え、NVHも悪化します。
第二に、圧損増大はポンプの軸受/メカニカルシールの摩耗やキャビテーションを誘発します。
第三に、添加剤枯渇や混合不具合は腐食/電食/スケールを加速し、二次粒子を増やして悪循環に陥ります。
第四に、診断が複雑化してダウンタイムや誤交換のリスクが増します。これらはすべて、適切な清浄度管理と予防保全で大幅に減らすことができます。
これからの視点:新技術と清浄度
電動化や高出力化に伴い、冷却回路はより高い熱流束にさらされ、チャネルの微細化/多段化が進みます。VDA 19.1はこうした動向も踏まえて改訂が進み、試験方法の選定や仕様化の根拠をいっそう明確化しています。
清浄度はコストではなく、熱マネジメントの確実性を買う投資であり、開発/調達/製造/アフターサービスを横断した共通言語として取り扱われるべきでしょう。
インテクノスのコンサルティングは、VDA19及びISO 16232の活用を含めた自動車業界の清浄度管理を支援しています。
高木 篤 / コンサルティングTOPチーム ― TOBIRA ―